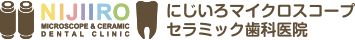-
夏の水族館で学ぶ!海の生物たちの歯の秘密
2024年7月18日(木)
夏休みが近づいてきましたね✨
皆さんは、旅行のご予定やレジャーの計画はお済みでしょうか?
その中でも暑い夏に人気のスポットの一つが、水族館です。
水族館は、海の生物たちとの触れ合いを楽しむだけでなく、教育的な一面も持っています。
そんな水族館での体験を通じて、歯科についても学べることがあることをご存知ですか?
◆夏休み前に知っておきたい!水族館で見る生物たちの歯
まず、水族館で目を引くのは、様々な種類の魚たちです。
例えば、サメやイルカなどの大きな海の生き物たちの歯に注目してみましょう。
サメは数百本もの鋭い歯を持ち、獲物を捕らえるためにその歯を絶えず交換しています。
一方、イルカはコーンのような形状の歯を持ち、獲物をしっかりと捕えるために使います。
これらの生物の歯の形状や機能は、それぞれの生態に適応して進化してきた結果です。

これと同じように、人間の歯もそれぞれ異なる役割を持っています。
前歯は食べ物を噛み切るために鋭く平らで、奥歯は食べ物をすりつぶすために広くて平らです。
このように、私たちの歯も生物学的に見ると非常に興味深い存在です。
さらに、水族館では歯のメンテナンスについて学ぶ機会もあります。例えば、ある種の魚やイルカは、歯のクリーニングを他の小さな魚に任せています。
これらの「クリーニングフィッシュ」は、寄生虫や食べかすを取り除くことで、大きな魚の歯を清潔に保ちます。
この関係は、自然界での歯科衛生の一例として、とても魅力的です。
◆海の生き物の歯と私たちの歯のつながり
このように、自然界でも歯の健康を保つための様々な工夫が見られます。
私たち人間も、歯の健康を保つために日々のケアが重要です。
夏休みの間は、アイスクリームやキャンディーなどの甘いものを食べる機会が増えるかもしれませんが、歯磨きを忘れずに行いましょう。
また、定期的な歯科検診も欠かせません。
虫歯や歯周病の早期発見・治療だけでなく、歯科医師による予防のためのアドバイスをさせていただきます。
◆水族館で知る歯の健康とケアのヒント
この夏休み、水族館を訪れる際には、ぜひ海の生物たちの歯にも注目してみてください。
そして、その学びを日々の歯のケアにも活かしてみましょう。
歯の健康は、私たちの全身の健康にも大きく影響します。
楽しい夏休みを過ごしつつ、健康な歯を保つための習慣を身につけましょうね。
にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院
-
インプラント治療をやらなきゃよかった!とならないためにも
2024年7月17日(水)
インプラント治療をやらなきゃよかった!とならないためにも
こんにちは。練馬区大泉学園にじいろマイクロスコープセラミック歯科です。今回は、多くの患者さんが抱える不安「インプラント治療をやらなきゃよかった!」という後悔を防ぐための重要なポイントについてお話しします。
インプラント治療の重要性
まず、インプラント治療の重要性について触れておきましょう。歯を失うことは、見た目だけでなく、咀嚼機能や発音にも影響を与えます。インプラントは、失った歯の機能を最も自然に近い形で回復させる方法として、現代の歯科治療において非常に重要な役割を果たしています。
しかし、「インプラント治療をやらなきゃよかった!」と後悔する患者さんも少なくありません。この記事では、そのような後悔を防ぐためのポイントを詳しく解説していきます。
1. 適切な歯科医院の選択
インプラント治療の成功は、施術を行う歯科医院の選択に大きく左右されます。練馬区大泉学園にじいろマイクロスコープセラミック歯科では、最新の設備と技術を導入し、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供しています。
マイクロスコープの活用
当院では、マイクロスコープを使用した精密な治療を行っています。マイクロスコープにより、肉眼では見えない細部まで確認しながら治療を進めることができ、より精度の高いインプラント埋入が可能となります。
セラミック素材の使用
また、当院ではセラミック製のインプラントも選択肢として提供しています。セラミックは生体親和性が高く、金属アレルギーの心配がない素材です。審美性にも優れているため、前歯部のインプラントにも適しています。
2. 十分な事前説明と理解
インプラント治療を後悔しないためには、治療内容を十分に理解することが重要です。当院では、以下の点について丁寧に説明を行っています。
– 治療の流れと期間
– 予想される結果と限界
– 費用と保険適用の有無
– 術後のケアと定期検診の重要性
患者さんの疑問や不安にしっかりと答え、十分な理解を得た上で治療を開始することで、後悔のリスクを大きく減らすことができます。
3. 適切な術前診断
インプラント治療の成功には、適切な術前診断が欠かせません。当院では、以下の検査を行い、患者さんの口腔内の状態を詳細に把握します。
CT検査
3次元のCT画像を用いることで、骨の状態や神経の位置を正確に把握し、安全で確実なインプラント埋入計画を立てることができます。
歯周病検査
インプラント治療の前に、歯周病の有無とその程度を確認します。必要に応じて、事前に歯周病治療を行うことで、インプラントの長期的な成功率を高めることができます。
4. 高度な技術と経験
インプラント治療の成功には、歯科医師の技術と経験が大きく影響します。当院の歯科医師は、インプラント治療に関する豊富な経験と高度な技術を持っています。
継続的な研修
最新の治療技術や材料に関する情報を常にアップデートするため、定期的に研修や学会に参加しています。これにより、患者さんに最適な治療を提供し続けることができます。
症例数の豊富さ
多くのインプラント症例を手がけてきた経験は、様々な状況に対応する力となります。当院では、難しいケースにも柔軟に対応し、高い成功率を維持しています。
5. アフターケアの重要性
インプラント治療は、埋入手術で終わりではありません。長期的な成功のためには、適切なアフターケアが不可欠です。
定期検診の実施
当院では、インプラント治療後も定期的な検診をお勧めしています。早期に問題を発見し、対処することで、インプラントの寿命を延ばし、快適な口腔環境を維持することができます。
ブラッシング指導
インプラント周囲の清掃は、天然歯とは少し異なる技術が必要です。当院では、患者さん一人ひとりに適したブラッシング方法を丁寧に指導しています。
6. 患者さんの生活習慣への配慮
インプラント治療の成功は、患者さんの生活習慣にも大きく影響されます。
禁煙指導
喫煙は、インプラントの成功率を低下させる大きな要因の一つです。当院では、必要に応じて禁煙指導も行っています。
生活のアドバイス
バランスの取れた食事は、口腔内の健康維持に重要です。カルシウムやビタミンDなど、骨の健康に必要な栄養素の摂取についてもアドバイスしています。
7. トラブルへの迅速な対応
万が一、インプラント治療後にトラブルが発生した場合でも、迅速かつ適切な対応が重要です。
メール相談窓口
当院では、患者さんの不安に対応するため、メール相談窓口を設けています。些細な疑問でも、すぐに相談できる環境を整えています。
緊急時の対応
痛みや腫れなどの症状が出た場合は、速やかに診察を行い、適切な処置を施します。早期対応により、大きなトラブルを防ぐことができます。
まとめ:後悔しないインプラント治療のために
インプラント治療は、失った歯の機能を回復し、豊かな生活を取り戻すための素晴らしい選択肢です。しかし、「インプラント治療をやらなきゃよかった!」と後悔しないためには、以下のポイントが重要です。
1. 信頼できる歯科医院を選ぶ
2. 治療内容を十分に理解する
3. 適切な術前診断を受ける
4. 経験豊富な歯科医師に施術してもらう
5. アフターケアを怠らない
6. 健康的な生活習慣を心がける
7. トラブル時は迅速に対応する
練馬区大泉学園にじいろマイクロスコープセラミック歯科では、これらのポイントを全て満たす高品質なインプラント治療を提供しています。最新のマイクロスコープ技術とセラミック素材を用い、患者さん一人ひとりに寄り添った治療を行っています。
インプラント治療をお考えの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。経験豊富な歯科医師が、あなたの口腔内の状態を詳しく診断し、最適な治療計画を提案いたします。
安心・安全なインプラント治療で、健康的で美しい笑顔を取り戻しましょう。練馬区大泉学園にじいろマイクロスコープセラミック歯科は、あなたの素敵な笑顔をサポートします。
ご予約・お問い合わせは、お電話またはウェブサイトからお気軽にどうぞ。皆様のご来院を心よりお待ちしております。
練馬区大泉学園のにじいろマイクロスコープセラミック歯科では経験豊富なインプラント認定医によるインプラント、オールオン4無料相談、無料メール相談を行っております。ご希望の方は、以下よりお申し込みください。


-
★2024年 商店街の夏祭りのお知らせ★
2024年7月11日(木)
みなさん、こんにちは♪
今年の夏(7〜9月)は、全国的に平年より高い気温が予想されていますね。
観測史上最も暑かった昨年に匹敵する暑さとなる可能性があるため、暑さ対策が重要です。
そんな暑い夏を楽しく乗り切るためにも、毎年恒例の商店街の夏祭りの日程が近づいてきましたので、みなさんにお知らせいたします。
今年の夏祭りも楽しいイベントが盛りだくさんです。
ご家族やお友達と一緒に、ぜひお越しください!
日時
2024年7月28日(日)午後 3:00~6:00場所
東大泉仲町銀座商店街※雨天決行/荒天中止


◆当院では、水ヨーヨー釣りを行います♪
カラフルな水ヨーヨーを釣りは、毎年子どもたちに大人気のイベントです。ぜひご自身で釣れたヨーヨーはお持ち帰りいただき、お家でもたくさん遊んでみてくださいね。
夏祭りでぜひ楽しんでほしい内容をいくつかご紹介します♪
◆わたあめとラムネ
夏祭りといえば、やっぱりわたあめとラムネ!ふわふわのわたあめと、冷たいラムネで暑さを忘れましょう。
甘いわたあめとシュワシュワのラムネは、お子さんも大人も楽しめますよ。
◆スーパーボールすくい
カラフルなスーパーボールがたくさん!どれだけすくえるか挑戦してみてください。
スーパーボールをすくうのはコツが必要で、大人もついつい夢中になってしまいます。
◆かき氷
暑い夏にぴったりのかき氷もご用意しています。野外で食べる冷たいかき氷で体を冷やして、元気に過ごしましょう。
◆午後3:40~4:00には、ウクレレの演奏があります。
心地よい音色が商店街に響き渡り、みなさんを癒してくれることでしょう。
◆また、参加型のイベントとして、こども太鼓を予定していますので、ぜひこの機会にご参加ください。
こども太鼓のお時間は、午後3:00~3:30、午後5:10~5:40になります。
その他にも楽しいイベントや出店が目白押しです♪
夏祭りは、我々の日頃の感謝の気持ちを込めて、みなさんに楽しんでいただくための大切なイベントです。
今年も、みなさんと一緒に素敵な夏の思い出を作りたいと思っています。
ご質問やお困りのことがありましたら、我々、にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院へ、お気軽にお声がけください。
それでは、7月28日(日)にお会いできるのを楽しみにしています★
-
口元の筋肉「舌筋」を鍛える「あいうべ体操」ご存知ですか?
2024年7月2日(火)
みなさん、こんにちは。
にじいろマイクロスコープセラミック歯科医院です。みなさんは、『あいうべ体操』という、舌の筋肉「舌筋」をはじめ口元の筋肉を鍛えられる体操をご存じでしょうか?
聞いたことある方は、『あいうべ体操』の正しいやり方を知っていますか?
〈あいうべ体操のやり方〉
あいうべ体操は「あ〜」「い〜」「う〜」「べ〜」と口を動かすだけの簡単な体操です。
声は出しても出さなくてもかまいません。
口をしっかりと大きく動かすのがポイントです。
10回を1セットとして、1日3セット行うと効果的と言われております。
行うタイミングは歯磨きの後や就寝前がおすすめです。
はじめは疲れたり、筋肉痛が出たりしますので、慣れるまでは2〜3回に分けた方が続けやすいかもしれません。
〈あいうべ体操の効果〉
口呼吸の予防・改善です!
正しい舌の位置は上あごのくぼみにピッタリとくっついている状態です。
正しい舌の位置のことを「スポット」といいます。
ところが、舌の筋肉が衰えると位置は下に下がってしまいます。
舌の位置が下に下がってしまうとポカンと口が開きやすくなってしまうのです。
あいうべ体操を行うことで口周りや舌の筋肉が鍛えられ、舌が正しい位置にくると自然と鼻呼吸になり口呼吸やポカン口の改善に繋がります。
☆口呼吸をやめることによる効果
・虫歯や歯周病のリスク低下
・いびき改善
・口臭やドライマウスの改善
・歯並びの改善
ここでポイント!
口呼吸は歯並びにも影響を及ぼします。
口が開きっぱなしになっていると下顎が常に下がっていることになり、同時に舌の位置も下がり口周りの筋肉が発達しません。
成長期に鼻を使わず口呼吸をする習慣が付いてしまうと、上の歯がきれいに並ぶスペースが不足し、歯がぎゅうぎゅう詰めになってしまう可能性があるため、結果として将来の歯並びにも影響していきます。
にじいろマイクロスコープセラミック歯科医院では、お子さまの定期検診の時に『リットレメーター』を使用しております。
(口腔機能発達不全症のお子さまが対象になります)
『リットレメーター』とは、口唇閉鎖力を測定できるものです。
あいうべ体操を継続していくと、だんだんお口の周りの力が鍛えられていくので、リットレメーターの数値も上がることが期待できます。
定期検診の時に一緒に確認していきましょう!
あいうべ体操はとても簡単でいつでもどこでも取り組むことができるトレーニングです。
日常に取り入れて継続していくことが大切になってきます。
是非ご自宅などでチャレンジしてみてください♪
引用:
-
お口の機能や発達を改善 歯科医院でのトレーニングのメリット
2024年6月7日(金)
◆「口腔機能発達不全症」とは
「口腔機能発達不全症」という言葉を耳にしたことはありますか?
簡単に説明すると、正しい姿勢+食べる、飲み込む、呼吸する、話す等のお口の機能が十分に発達していない状態のことをいいます。
それによりどのようなことが起こるかというと、むし歯のリスクが上がる、歯並びが悪くなる、口呼吸になる、睡眠が悪くなる、ADHD的症状が出る等のことが挙げられます。
お口の機能が低下しているということは、お口の健康や姿勢、集中力の低下、お顔の印象など、様々な影響を引き起こす可能性があります。

以前もお伝えしたように、「加齢による口腔機能の変化のイメージ図」を見ていただくと、生涯の健康のための基礎は小児期に築かれ、年齢と共に口腔機能が下降していくことがわかるかと思います。
よろしければ前回のブログもご参照ください。
https://www.nijiiro-shika.jp/blog/post/2827/
➡歯科医院でのトレーニングにより、お子さまのお口の機能を向上し、成長や発達に伴う改善を目指していきませんか?
◆「口腔機能発達不全症」に当てはまる?
・お口がポカンと開いている
・食べこぼすことが多い
・鼻呼吸ではなく口で呼吸をしている
・滑舌が良くない
これらに当てはまることがあれば、「口腔機能発達不全症」の可能性があります。
お子さんのお口の機能や成長、発達が気になる方は、当院のスタッフにご相談ください。
「口腔機能発達不全症」は小児期からのトレーニングで改善でき、機能発達の促進を期待できます。
例えば、親子一緒にできる遊びのような舌のトレーニングは、とても有効ですよ。
◆トレーニングのゴールは?
このトレーニングの最終的な着地点は何かというと、歯並びをよくしたり、正しい噛み合わせを求めるものではありません。
トレーニングを行うことで、正しい舌の使い方を身につけ、食べる、話す等の機能面を発達させていくことが理想的です。
トレーニングは楽しく長く続けることがポイントです。
少しずつコツコツ続けることで、効果を感じてみてくださいね。
大人になってからも、遅いことはありません。
お口の機能を鍛えることで、いつまでも若々しくいたいものです。
親子でお口周りの機能を正しく保っていきましょう。
にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院
-
食事が口腔健康に与える影響~体質改善の秘訣~
2024年5月28日(火)
こんにちは。
日に日に強まる日差しに、早くも夏の訪れを感じる季節になりましたね。
梅雨入りも間近ですが、体調を整えて過ごしていきましょう。
今回は、食事内容と口腔健康の関係に焦点を当ててお伝えいたします。
食事は私たちの体質や健康に大きな影響を与えますが、普段の食生活で、バランスの取れた食事を意識していますか?
食生活を意識することは、ご自身の体調を整えてくれるだけでなく、口腔健康にも欠かせません。
例えば、砂糖や酸性食品を過度に摂取すると、歯のエナメル質が脆くなり、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
こうした問題を防ぐためには、バランスの良い食事が重要になります。
体質改善や口腔健康を考える上で、食事内容に工夫を加え、栄養バランスを整えることで、歯や歯ぐきを健康に保つことができますよ。

歯や歯茎を健康に保つためには?
カルシウムやビタミンCが重要です。
カルシウムは歯を強化し、ビタミンCは歯茎の健康をサポートします。
以下に、それらの栄養素を豊富に含む食べ物をご紹介しますので、参考にしてみてください。
カルシウムを多く含む食品
牛乳やチーズ
ヨーグルト
豆腐
ホウレン草やかぼちゃ
アーモンドや大豆
ビタミンCを多く含む食品
オレンジやレモン
イチゴやキウイフルーツ
ピーマンやトマト
ブロッコリーやカリフラワー
ピーマンやパセリ
日常からカルシウムやビタミンCを豊富に含む食材を積極的に摂取し、口腔内の健康状態を維持していきましょう。
今回は、食事が口腔健康に与える影響と体質改善の重要性についてご紹介しました。
当院では、口腔内の健康だけでなく、食生活や生活習慣にまで目を向けたアプローチを行い、全身の健康のサポートができるように努めています。
口腔健康を考える際には食事も大切な要素の1つです。
健康な生活を送るため、食事の重要性を改めて意識してみてくださいね。
ぜひ日々の食生活に気を配り、健康な笑顔を保ちましょう。
それでは、次回のブログ更新もお楽しみに♪
-
アマルガムとは?~適正な歯科治療の選択を~
2024年5月15日(水)
アマルガムとは?
アマルガムは、歯科用水銀アマルガムの略で、水銀を含む金属合金のことです。
主な成分は、水銀50%、銀35%、スズ9%、銅6%、少量の亜鉛からできています。
アマルガムは抗菌性が高く、治療後に再び虫歯ができにくいという理由からも、以前は歯科医院で一般的に使用されていました。
また、柔らかい素材で歯の穴に密着しやすく、充填後は強度が増すため、長持ちする利点もあります。
ただし、水銀の安全性への懸念から、日本では2016年に保険適用外となりました。

アマルガムが体内に与える影響
アマルガムは、最初は「安全で耐久性が高い」と考えられていましたが、実際には口の中で劣化し、腐食していきます。
アマルガムは、微細な刺激で気化し、劣化すると水銀を含む蒸気が発生し、体内に吸収されます。
この水銀は他の歯科金属と同様にアレルギー反応を引き起こし、血液を通じて全身に広がり、さまざまな症状を引き起こす可能性があるのです。
水銀は非常に有毒のため、口内炎、歯肉炎、蕁麻疹、アトピー性皮膚炎、頭痛、めまい、不眠症、感覚異常、免疫性疾患などの症状が現れる可能性があります。
世界的にみるアマルガム規制の現状
また、アマルガムには、不妊の原因となる可能性や胎児や母乳に影響を及ぼす恐れがあるとの報告もされています。
そのため、1980年代から1990年代にかけて、スウェーデンやイギリスでは、妊婦にアマルガムを適用しないよう注意が喚起されました。
デンマークやイギリスでは、妊婦を含む全ての患者に対してアマルガムの使用が禁止され、水銀を使用しない新しい歯科材料が普及し、世界的にアマルガムの規制が進んでいます。
このようにアマルガムの使用は減少傾向にありますが、一部地域ではまだ使用されているところもあります。
先述しましたが、日本では2016年4月に保険適用から外れたため、現在、アマルガムはほとんど使用されていません。
にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院での取り組み
歯科のつめ物や被せ物の素材開発や治療技術は進化しており、金属以外の白い素材を使用することが可能です。
保険適用の範囲では、歯科用プラスチックが一般的に使用され、保険適用外では、オールセラミックやジルコニアなどの素材が選択肢として使用されているのが現状です。
これらの素材は見た目が自然であり、かつ耐久性や安全性にも優れています。
当院では、セラミックなどの体に優しい素材を使い、自然で綺麗な白色の詰め物・被せ物を取り扱っています。
天然歯のように自然な見た目を再現でき、金属を使わずに治療ができるので、金属アレルギーや、歯肉が変色する心配がありません。

にじいろマイクロスコープ・セラミック歯科医院では、全ての患者様に安心で安全な歯科医療サービスを提供するため、徹底した衛生管理を行っています。
ご興味がありましたら、お気軽にご相談ください。
-
インプラント治療のデメリットは何ですか?
2024年5月8日(水)
インプラント治療のデメリットは何んですか?
みなさん、こんにちは。練馬区大泉学園にじいろマイクロスコープセラミック歯科です。
今回は、インプラント治療のデメリットについてお話ししたいと思います。インプラント治療は、失った歯の機能を回復するために有効な治療法ですが、いくつかのデメリットがあることも知っておく必要があります。
- 治療期間が長い インプラント治療は、手術から最終的な歯の装着まで、数ヶ月から半年以上かかることがあります。手術後、インプラントが骨と結合するまでの期間(オッセオインテグレーション)が必要で、その間は仮歯を装着することになります。治療期間が長いことで、生活に支障をきたす可能性があります。
- 手術が必要 インプラント治療では、歯茎を切開してインプラントを骨に埋入する手術が必要です。手術に伴う痛みや腫れ、出血などのリスクがあります。また、手術後の回復期間中は、日常生活に制限が生じることもあります。
- 費用が高い インプラント治療は、保険適用外の自由診療となるため、費用が高くなる傾向があります。1本あたり30万円から50万円程度かかることが多く、複数本のインプラントが必要な場合は、さらに高額になります。経済的な負担が大きいことがデメリットの一つです。
- 感染や拒絶反応のリスク インプラント手術後に、感染や拒絶反応が起こる可能性があります。適切な手術手技と術後管理により、このようなリスクを最小限に抑えることが重要ですが、完全に排除することはできません。感染や拒絶反応が起こった場合、インプラントを撤去しなければならないこともあります。
- メンテナンスが必要 インプラント治療後は、定期的なメンテナンスが必要です。インプラント周囲の歯垢や歯石を除去し、歯茎の健康状態をチェックする必要があります。メンテナンスを怠ると、インプラント周囲炎などの合併症を引き起こす可能性があります。
- 骨の量や質によっては適用できない インプラント治療を行うためには、十分な骨の量と質が必要です。骨の量が不足している場合や、骨の質が悪い場合は、インプラント治療が適用できないことがあります。このような場合、骨造成術などの追加治療が必要になることもあります。
- 神経や血管の損傷リスク インプラント手術では、神経や血管の損傷リスクがあります。特に下顎骨では、下歯槽神経や舌神経の損傷に注意が必要です。神経損傷が起こると、しびれや感覚異常などの後遺症が残ることがあります。
- 審美性に限界がある インプラント治療では、天然歯に近い見た目を再現できますが、完全に同じにはなりません。特に、前歯部のインプラントでは、歯茎の形態や色調の違いが目立つことがあります。審美性に対する期待値が高い場合、満足度が低くなる可能性があります。
- 噛み合わせの調整が難しい インプラントは、天然歯と比べて感覚が鈍いため、噛み合わせの調整が難しいことがあります。インプラントの位置や角度が適切でないと、咬合力の分散が不均等になり、他の歯や顎関節に負担がかかることがあります。
- 長期的な予後が不明確 インプラント治療は、比較的新しい治療法であるため、長期的な予後に関するデータが不足しています。インプラントの寿命は、個人差が大きく、10年から20年以上持続することもありますが、将来的に再治療が必要になる可能性もあります。
- 喫煙者や糖尿病患者のリスク増加 喫煙者や糖尿病患者は、インプラント治療の成功率が低下する可能性があります。喫煙は血流を悪化させ、傷の治りを遅らせます。また、糖尿病は免疫機能に影響を与え、感染リスクを高めます。これらの患者さんには、治療前に禁煙や血糖コントロールの改善が推奨されます。
- アレルギーの可能性 チタン製のインプラントは生体親和性が高いとされていますが、まれにチタンアレルギーを引き起こす可能性があります。アレルギー反応が出た場合、インプラントの除去が必要になることもあります。事前のアレルギー検査を行うことで、このリスクを軽減できます。
- 咬合力の調整期間 インプラント治療後、患者さんは新しい咬合力に慣れる必要があります。天然歯と異なり、インプラントには歯根膜がないため、咬合圧を感じにくくなります。この調整期間中は、過度な力がかからないよう注意が必要で、徐々に硬い食べ物に慣れていく必要があります。
- 技術者の技量による差 インプラント治療の成功率は、歯科医師の技術や経験に大きく左右されます。高度な技術と豊富な経験を持つ歯科医師による治療を受けることで、より良好な結果が期待できます。当院では、最新の技術と豊富な経験を組み合わせ、最高品質のインプラント治療を提供しています。
- これらの追加のデメリットや注意点を理解することで、患者様はより十分な情報を得た上で治療を決断することができます。当院では、これらのリスクを最小限に抑えるため、徹底した術前診断と綿密な治療計画を立てています。また、患者様一人ひとりの状態に合わせたカスタマイズされた治療アプローチを提供し、最適な結果を追求しています。
以上が、インプラント治療のデメリットです。しかし、これらのデメリットを理解した上で、適切な症例選択と治療計画を立てることで、インプラント治療のメリットを最大限に活かすことができます。
当院では、マイクロスコープを使用した精密な手術と、セラミック素材を用いた審美性の高い上部構造により、インプラント治療の質の向上に努めています。また、治療前のカウンセリングでは、患者様のお口の状態や希望をしっかりとお伺いし、デメリットも含めた十分な説明を行った上で、最適な治療法をご提案いたします。
インプラント治療をお考えの方は、ぜひ一度当院にご相談ください。豊富な経験と最新の設備を活かし、患者様のQOL(生活の質)の向上を目指して、最適なインプラント治療を提供いたします。
練馬区大泉学園のにじいろマイクロスコープセラミック歯科では経験豊富なインプラント認定医によるインプラント、オールオン4無料相談、無料メール相談を行っております。ご希望の方は、以下よりお申し込みください。


-
オールオン4は糖尿病でもできますか??
2024年5月5日(日)
オールオン4は糖尿病でもできますか??
糖尿病を抱えている方にとって、歯科治療は特に重要な問題です。糖尿病は全身の健康に影響を与えるだけでなく、口腔内の健康にも大きな影響を及ぼすためです。そのため、糖尿病患者の方が歯を失ってしまった場合、インプラント治療を検討する際には、慎重に判断する必要があります。今回は、糖尿病患者の方がオールオン4を受けることができるのかどうかについて詳しく解説していきます。
糖尿病とオールオン4の関係
オールオン4は、上顎または下顎の歯を全て失った方に対して、わずか4本のインプラントで固定式の義歯を装着する革新的な治療法です。この治療法は、従来のインプラント治療と比べて、手術回数が少なく、治療期間も短いことが大きな利点となっています。
しかし、糖尿病患者の方がオールオン4を受ける際には、いくつかの注意点があります。糖尿病は、インプラント治療のリスクを高める可能性があるためです。
糖尿病がインプラント治療に与える影響
糖尿病は、以下のような理由からインプラント治療のリスクを高める可能性があります。
- 感染リスクの増大 糖尿病患者は、感染に対する抵抗力が弱くなっているため、インプラント手術後の感染リスクが高くなります。
- 骨の治癒力の低下 糖尿病は、骨の治癒力を低下させる可能性があります。インプラントが骨と結合するためには、骨の治癒力が重要となります。
- 血糖コントロールの難しさ インプラント手術は、体に大きなストレスをかけます。このストレスにより、血糖値が上昇しやすくなります。血糖コントロールが難しい状態では、手術後の回復が遅れる可能性があります。
糖尿病患者がオールオン4を受けるための条件
糖尿病患者の方がオールオン4を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 血糖コントロールが良好であること オールオン4を受ける前に、血糖値が安定していることが重要です。HbA1c値が7%以下に維持されていることが理想的です。
- 糖尿病の合併症がないこと 網膜症、腎症、神経障害などの糖尿病合併症がある場合、オールオン4のリスクが高くなります。合併症がない、または軽度である方が適しています。
- 禁煙すること 喫煙は、インプラント治療の成功率を下げる大きな要因です。オールオン4を受ける際には、禁煙が必須となります。
- 定期的な歯科検診を受けること オールオン4を受けた後は、定期的な歯科検診とメンテナンスが重要です。特に糖尿病患者の方は、感染リスクが高いため、こまめな検診が必要不可欠です。
糖尿病患者のためのオールオン4治療
練馬区大泉学園にある当院では、糖尿病患者の方のためのオールオン4治療を提供しています。当院では、カウンセリングの段階から、患者様の全身の健康状態を詳しく把握し、安全で確実な治療計画を立てることを心がけています。
最新の設備と技術
当院では、CT撮影や顕微鏡を用いた精密な診断と治療が可能です。これにより、インプラントの埋入位置や角度を正確に計画し、手術のリスクを最小限に抑えることができます。
糖尿病専門医との連携
当院では、糖尿病専門医との連携体制を整えています。オールオン4治療の前後には、患者様の血糖コントロールが重要となります。専門医との連携により、安全で確実な治療を提供いたします。
丁寧なアフターケア
オールオン4治療後は、定期的なメンテナンスが必要不可欠です。当院では、患者様一人ひとりに合わせたアフターケアプランをご提案し、長期的な口腔内の健康維持をサポートいたします。
まとめ
糖尿病患者の方がオールオン4を受けることは可能ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。血糖コントロールが良好で、合併症がない方が適しています。また、禁煙と定期的な歯科検診も重要なポイントです。
練馬区大泉学園にじいろマイクロスコープセラミック歯科では、糖尿病患者の方のためのオールオン4治療を提供しています。最新の設備と技術、糖尿病専門医との連携、丁寧なアフターケアにより、安全で確実な治療を実現いたします。
歯を失ってしまった糖尿病患者の方も、ぜひ一度当院にご相談ください。患者様の健康な笑顔を取り戻すために、私たちは全力でサポートいたします。
練馬区大泉学園のにじいろマイクロスコープセラミック歯科では経験豊富なインプラント認定医によるインプラント、オールオン4無料相談、無料メール相談を行っております。ご希望の方は、以下よりお申し込みください。


-
インプラントオールオン4をできない人はどのような人ですか?
2024年5月5日(日)
インプラントオールオン4をできない人はどのような人ですか?
インプラントオールオン4は、多数の歯を失った方におすすめの画期的な治療法ですが、残念ながら全ての方に適しているわけではありません。今回は、インプラントオールオン4をできない人について解説していきます。
- 重度の歯周病に罹患している方
インプラントオールオン4は、インプラントを4本顎骨に埋入し、それを土台にブリッジを装着する治療法です。しかし、重度の歯周病により顎骨が著しく吸収してしまっている場合、インプラントを支えるのに十分な骨量が確保できないため、インプラントオールオン4の適応となりません。歯周病の治療を優先し、骨の再生を図ることが必要です。 - 全身的な健康状態が良くない方
糖尿病や骨粗鬆症、免疫機能の低下などの全身疾患を抱えている方は、インプラント手術のリスクが高くなります。これらの疾患は、インプラントの osseointegration(オッセオインテグレーション:骨とインプラントが結合すること)を阻害し、インプラントの失敗や感染症のリスクを高めます。手術前に全身状態を改善し、主治医との連携が不可欠です。 - 喫煙者の方
喫煙は、インプラント治療の成功率を大きく低下させる要因の一つです。喫煙により口腔内の血流が悪化し、創傷治癒が遅延します。また、喫煙者はインプラント周囲炎のリスクも高くなります。インプラントオールオン4を検討している喫煙者の方は、禁煙に取り組むことが強く推奨されます。 - 顎骨の高さや幅が不十分な方
インプラントオールオン4は、上顎の場合は顎骨の前方部に、下顎の場合はオトガイ孔よりも前方の骨に、インプラントを斜めに埋入します。これにより、骨量の少ない方でもインプラントによる補綴治療が可能になります。しかし、顎骨の高さや幅が極端に不足している場合は、インプラントを適切な位置に埋入することが難しくなります。このような場合、骨造成手術を併用したインプラント治療や、従来の可撤性義歯を選択することになります。 - ブラキシズム(歯ぎしり)の方
ブラキシズムは、睡眠中や無意識のうちに歯ぎしりや食いしばりを繰り返す習癖です。強い力が繰り返し加わることで、インプラントに過大な負荷がかかり、インプラントの緩みや破損、さらには顎骨の吸収を引き起こす可能性があります。ブラキシズムの方は、インプラントオールオン4の適応には慎重になる必要があります。マウスガードの使用や、ブラキシズムの原因となる心理的ストレスのコントロールが求められます。 - 経済的な事情で高額な治療費を負担できない方
インプラントオールオン4は、従来のインプラント治療と比較して短期間で歯を回復できる優れた治療法ですが、その分、治療費が高額になる傾向があります。経済的な理由から治療費を工面できない方は、他の治療オプションを検討する必要があります。部分入れ歯や総入れ歯、インプラントオーバーデンチャーなど、それぞれの方の予算や要望に合わせた治療法をご提案いたします。
以上のように、インプラントオールオン4は多くの方に適した治療法ですが、全ての方に適応できるわけではありません。治療を検討する際は、お口の状態だけでなく、全身の健康状態や生活習慣、経済的な事情など、様々な要因を考慮する必要があります。
にじいろマイクロスコープセラミック歯科では、患者様お一人おひとりのお口の状態や要望を丁寧にお伺いし、最適な治療オプションをご提案いたします。インプラントオールオン4だけでなく、従来のインプラント治療や入れ歯、さらには審美歯科治療まで、幅広い治療に対応しております。
マイクロスコープを使用した精密な診査と治療、CAD/CAMを活用した高品質な補綴物の製作、CT画像による緻密な治療計画の立案など、最新の設備と技術を駆使し、患者様に最高水準の歯科医療をお届けいたします。
歯を失ってしまったことでお悩みの方、インプラントオールオン4をご希望の方は、ぜひ一度にじいろマイクロスコープセラミック歯科にご相談ください。熟練の歯科医師と歯科技工士が連携し、患者様の素敵な笑顔を取り戻すお手伝いをさせていただきます。皆様のご来院を心よりお待ちしております。
練馬区大泉学園のにじいろマイクロスコープセラミック歯科では経験豊富なインプラント認定医によるインプラント、オールオン4無料相談、無料メール相談を行っております。ご希望の方は、以下よりお申し込みください。


- 重度の歯周病に罹患している方
ブログBLOG
インプラント オールオン4 無料相談・カウンセリング 練馬区大泉学園
大泉学園駅の歯科・歯医者|にじいろマイクロスコープセラミック歯科医院